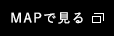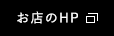探す
それぞれ明治通り沿いの神宮前にフラッグシップショップを構えるJohnbullとTAKEO KIKUCHI。両者を代表してJohnbullのものづくりに携わるパターンクリエイター中村里美氏とTAKEO KIKUCHIクリエイティブディレクター菊池武夫が「神宮前×大人×ファッション」をキーワードに語り合いました。「このエリアを盛り上げたい」という二人の思いから、両氏が注目する神宮前スポットも一緒にご紹介します。
第2回:次の世代にも残したい意識や感覚
かつては、“大人に憧れる”文化だった
70〜80年代頃のファッション文化を作っていた主役は、10代でしたか?それとも、20代でしたか?
中村:
いや、もっと範囲が広いと思います。
菊池:
たぶん、20代後半ぐらいから30代ぐらいだったと思う。
中村:
私たちは10代後半でしたけど、もう(洋服などが)欲しくて、欲しくて。昔は、若い人が大人に憧れる文化でしたね。私が子供の頃は、大人を見習いなさいと躾けられてきましたから、ファッションに関しても「大人を見習って、センスを磨く」という文化だったんですよ。
菊池:
今は逆かもしれないね。
中村:
テリー伊藤さんなどは、若い子のそういう対象の代表格でしたね。今は、大人の種類も多様的になり、理解のある大人になろうという流れに変わってきましたよね。ただ、昔に戻るという意味ではなくて、個人的には相変わらず昔のことが好きなんです。私が常日頃考えている哲学としては、若い人が大人を目指すようなファッションであればいいなと思っています。

“個”という意識とファッション
今は、何かそういう意識が薄い気がしますね。
中村:
団体意識がとても強いじゃないですか。
菊池:
強いね。日本の場合、特にそれを感じる。
中村:
農耕民族的ですよね。私たちは“個”でありたいという意識がすごく強い時代の中で、そうやって教えられてきましたから。“個”であろうとする。
菊池:
そうそう。
中村:
ファッションでも人と同じものではなくて、同じものでも違う何かを意識していた。今は同じでいればいいというか、一緒であることに安心感を抱くという感じですよね。
菊池:
これは、昔からの農耕民族特有の国民性ですよ。例えば、昔も(車の)バンが流行ったら、日本中がみんなバンだものね。外国では、各々の個性があるからあり得ない。でも、日本人は平気なんですよ。
自分を見つめて洋服を着るのでなくて、人が納得できればいいという意識ですよね。集団の一部でありたい、という思いが強いんじゃないかな。これだけは打破したい。
中村:
そうですよね。その思いは、すごくあります。初めてファッションを感じて刺激を受けた部分って「人と一緒じゃいけないんだな」ということでした。
普通に服を着るだけなら、例えば(大量生産の)ファストファッションブランドも、若い人たちはちゃんとブランドとして認知されています。それはそれで良いと思うんです。ただ、ファッションを目指すという感覚や自己表現をするのと、普通に服を着る事は全く違うと思います。そういった事を受け入れる感性が弱まっているのでは、とすごく感じます。
そういった状況の中で、一生懸命活動しているデザイナーさんが日本で活躍できないというのも、とてもジレンマを感じますね。みんなでそういう人を応援し、ファッションを育てて行こうという感覚もすごく薄れている気がします。結局、大人ばかりが頑張っているという印象がありますね。

目で見て、歩いて、手で触る、ということ
海外の話も少し出ましたが、日本でインターネットもなかった時代は、どこで海外文化に触れていたんでしょうか?
菊池:
昔は、今以上に海外文化というのが、すごく意識されていたかもしれないですね。僕らは、海外のあちこちに行きました。昔は、実際に行って、触れて、それを紹介するような形になっていたかな。
中村:
昔は、ファッション紙も今みたいにカタログ紙っぽくなかったですよ。
菊池:
そうだね。ニュースやノウハウとかの記事があった。
中村:
菊池先生などが実際に行かれて発信していた情報を収集して、自らもいろんな所に見に行きましたね。あとは、クチコミからも収集していました。歩いて感じる、目で見て感じる、手で触れて感じる、そういったことは(実際に)行かなければ分からないですしね。
最近よく感じるんですけど、インターネットで調べ物をして、何かを紐解こうとしても欲しい情報が出てこないんです。
菊池:
本当にそう。こういう仕事に携わっている人はみんな言っていますよ。証拠になるものや写真もほとんど残ってないし、こういう事があったという話も(インターネット上には)残ってないし。それをどうやって、外国のようにいろんな形できちんと残していって、積み重ねていけるか問題ですよね。そうやっていくと、文化が本当の意味で定着できるんですよ。日本の場合、過去のことがほとんど出てこない。

その意味では、インターネットは同じような表層的な情報が拡散していて、どこに行っても同じ程度の情報の深さという印象ですね。昔は皆さん何か知りたければ、本を見に行かなければいけなかったんですね。
菊池:
今は、その時間を持つ人もそんなにいないんじゃない。
中村:
あとは、目で見て、歩いて、手で触る、ということですよね。
菊池:
そう、感じないとね。
中村:
私たちは手で考えるので。今の若い人達と一緒に仕事をすると、彼らの感覚は鋭くないと感じます。良い部分もいっぱいあるんですけれどね。感性が弱まっているというか。
例えば、何かを見に行く時というのは、そこに至る時間とどうしても見たいという感情、欲望があって、道すがらその想像を膨らませながら行くという感じでした。しかも、行っても、それが全部手に入る訳ではないですから。見たものを覚えて帰って、また忘れないように見に行って、それを繰り返しながら形を作っていました。困った時に手で考える、ということに今でも頼るところはあります。
菊池:
それは共通ですよ。僕はちょっと先輩ですけれど、ずっとそれで悩んでいる。見ているから、知識では分かるんですよ。でも、それらが一体なんなのかと置き換えた時に、知識や情報を自分の中で消化するという事がとても難しい。
中村:
そうですね。ですので、私は情報をシャットアウトしています。逆に邪魔になるので、なるべく見ない、聞かない。例えば先生と一緒に仕事させて頂いていても、そうしないとすっと素直に(必要な情報が)入っていかないんですよ。余分な情報があると、そこに基づいて理解しようとしてしまって、本来伝えたいことだけをキャッチすればいいはずの感覚が弱まるんです。ですので、インターネットも一時は面白くて見ていたんですけど、今は本当に調べものや辞書代わりに使う程度であまり使わないです。
菊池:
30代もしくはもっと若い人達が、そういうことを踏まえて、これからを築き上げて行ったらまた変わるんじゃないかな。特にインターネットでは、今はただ基本的な情報が並んでいるだけで、知識としては使えるかもしれないけど、そこから考えるという作業がほとんど出来ていないよね。その悩みを、僕自身もずっと抱えているんです。
中村:
インターネットは無機質ですから、空気を感じながら見て感動することはないんですよ、やっぱり。実際のものにたどり着く時の言いようもない、何とも言えない感覚がありますよね。それを届けるのが仕事なので、そこの手を抜いてしまうのはよくない、と言わないとだめだなと思います。
インターネットから出るものでは、枝はできないと思うんです。生身の人間から生み出すものからは、枝ができる。だから、なるべくシャットアウトしています。もちろん、SNSとかは情報を収集するためにやっていますよ。ただ、そこから何かを得るということはないですね。コレクション情報もあえて見ないようにしています。
菊池:
僕も全く見ない。本や雑誌はほとんど見ないですよ。
中村:
実際に生で見るのとは全然違うから。
菊池:
全然違う。その時の自分が感じていることが一番大事。そこから得たもので、自分がどう思うかが一番大事ですから。
中村:
そうそう。
-
MORE

JACKET ¥37,000 / T-SHIRT ¥7,400 / EASY PANTS (Johnbull × 40CARATS&525) ¥21,000
菊池:このホテルには、行ったことがあります。中も全部案内してもらいました。東京にありそうなのに、今までこういうホテルは無かったですよね。他のホテルと違って、ゆったりしていて、いろんな人が多目的に集まっている空間です。ヨーロッパでも、こういうスタイルのホテルが普及してきていますね。ようやく東京にも来た、という感じです。
中村:とても良いコンセプトのホテルですよね。こういった場所にどんどん人が集まってくるのは、すごく良い事だなと思います。一人でいる事を不安に感じる若者も多いようなので、自然と集まれる場所があるのはすてきですね。
- 表示モード
- スマートフォン | PC





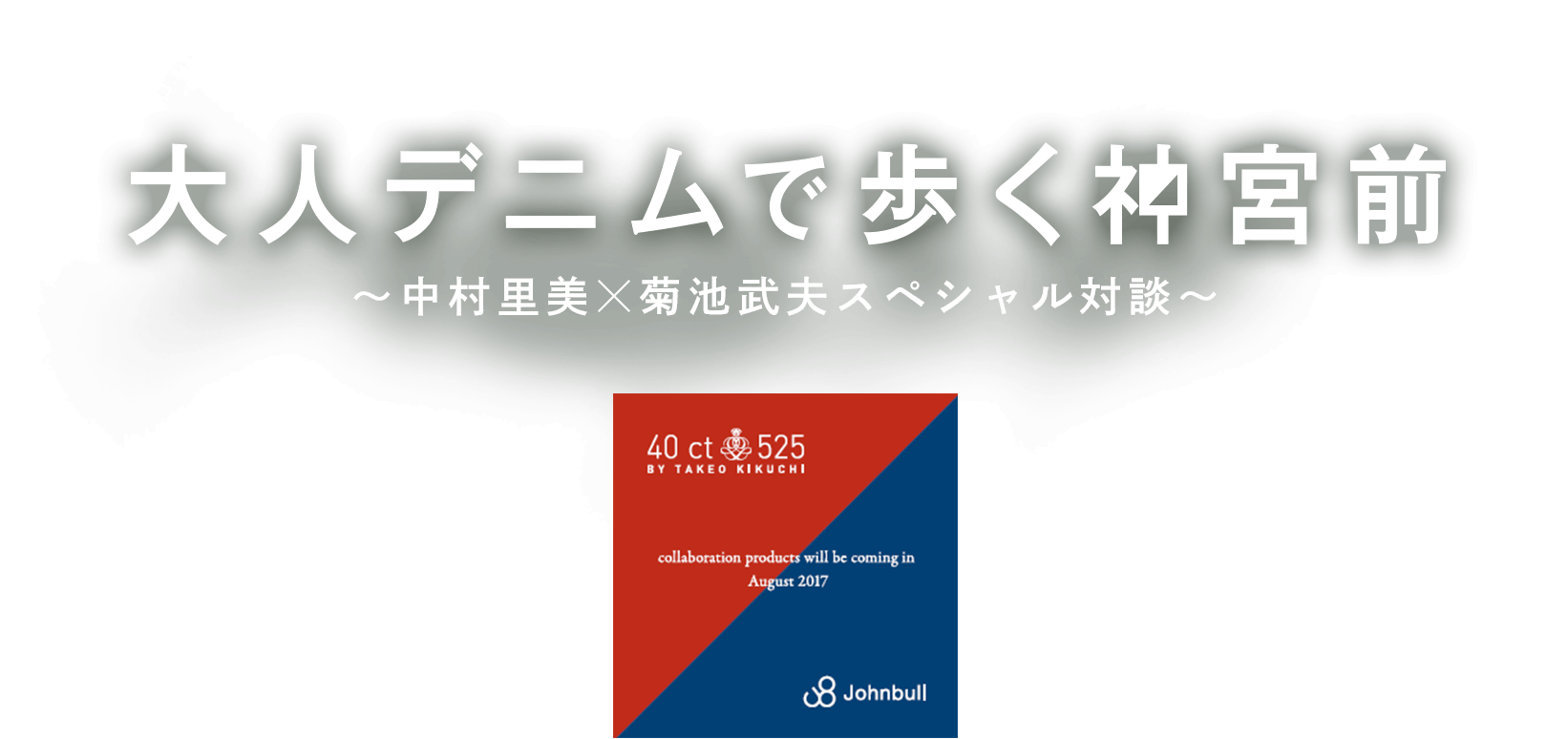

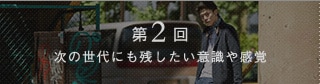







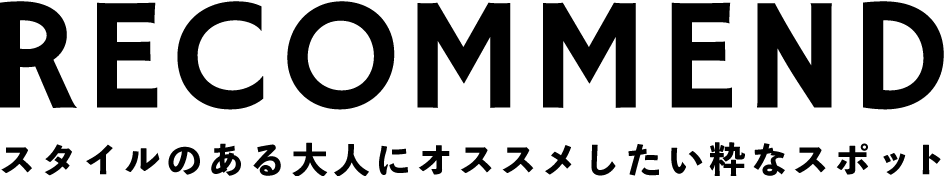

 03-5766-3210
03-5766-3210